皆さん、書店は好きですか。
筆者は本が好きですから、書店も好きです。
でも、最近、書店がどんどん消えていっていますね。
「街から書店が消える」。この予言は決して誇張ではありません。
小島俊一氏の著書『2028年街から書店が消える日』や山内貴範氏の『ルポ書店危機』は、
書店を取り巻く現状と未来を鋭く描き出しています。
どちらの本も、紙の書籍が重要であることを認識しながら、書店が直面する厳しい状況を冷静に分析していますね。
現在、書店は全国的に減少を続けています。
統計によると、1990年代には2万店舗以上あった書店が、2020年代には1万店舗を切り、さらにそのペースは加速しています。
この現象の背後には、電子書籍の普及、ECサイトの台頭、そして読書習慣の変化があります。
書店の危機とその現実とは?
書店消滅の主な要因

書店が消えつつある理由は多岐にわたりますが、大きく分けると次の3つが挙げられます。
1. デジタル化の進展
インターネットの普及により、書籍のデジタル化が進みました。
電子書籍はスマートフォンやタブレットで手軽に読める上、紙の本より安価で、場所を取らないというメリットがあります。
また、デジタルプラットフォームでは書籍だけでなく、
ニュースやブログ、SNSといった代替的な情報源も豊富で、活字文化そのものが多様化しています。
2. ECサイトの影響
Amazonをはじめとするオンライン書店の台頭は、書店経営に大きな影響を与えました。
特に地方の書店は、商品の豊富さや迅速な配送を武器にするECサイトに太刀打ちできず、
閉店に追い込まれる例が増えています。
加えて、書籍以外の商品の購入やレビュー閲覧が可能なオンラインプラットフォームは、
消費者にとって便利で魅力的です。
3. 社会と文化の変化
近年、読書の習慣そのものが希薄になりつつあります。
スマートフォンの普及で短時間の動画やSNS投稿が娯楽の主流となり、
長時間を費やす読書の優先順位が下がっているからでしょう。
特に若年層の間では、読書を日常的に行う人が減少しているというデータもあります。
逆に漫画やアニメなどを好んで観ているようですけどね。
書店が果たす役割とは?
書店は単なる「本を売る場所」ではありません。
地域に根ざした文化拠点としての役割も担っています。
個人経営の書店では、書籍の選書やイベント企画を通じて、地域住民との交流が行われています。
特に、地元作家の紹介や子ども向けの読書会など、書店ならではの取り組みは電子書籍やECサイトでは再現できない価値があります。
また、書店は「偶然の出会い」を提供する場でもあります。
棚に並ぶ本の中から、特に意識していなかった一冊に出会うことができるのは、書店ならではの体験です。このような偶発性が、読者にとって新たな知識や興味を広げるきっかけとなります。
筆者も書店で立ち読みして、これはおもしろそうだな、と思って買うケースも多いですからね。
書店の未来を守るために
書店の消滅を防ぐためには、書店自身の努力だけでなく、社会全体での協力が必要でしょう。
1. 書店の進化
書店は従来の形にとらわれず、新しいモデルを模索する必要があります。
カフェを併設した書店や、イベントスペースとしての機能を持つ店舗は、
単なる販売の場を超えて顧客に新しい価値を提供しています。
専門性を持ち、顧客に寄り添った提案ができる書店が、読者の支持を得る可能性があるということでしょう。
2. 地域との連携
書店は地域の文化と密接に結びつくことで、存在意義を高められます。
地元企業や自治体と連携し、街おこしイベントや教育活動の拠点となることで、地域住民との結びつきを強化できますから。
ただ、これについては連携が必要ですし、そういう企画力のある人材が必要でしょうね。
これまでは書店に本を並べておけば、本が売れたのかもしれませんが、そういう時代ではなくなったのかも。
地域情報になりますが、筆者が暮らす茨木市のJR千里丘駅前にあった「田村書店」も、2024年10月27日に閉店しました。

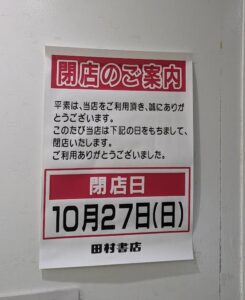
その後、この店舗の後にはまだ何も入っていませんね(11月末現在)。
本好きの筆者には便利でしたが、残念です。
そういえば、阪急南茨木駅前にあった「田村書店」も消えましたから、
書店が消えている現実は身近に感じていますね。
3. 読書文化の復活
今後、読書の魅力を次世代に伝える取り組みも重要でしょう。学校や家庭での読書習慣を奨励するだけでなく、SNSや動画コンテンツを通じて本の魅力を発信する方法も効果的です。若い世代に「本を読むことの楽しさ」を届ける努力が欠かせません。
書店を消さないために、私たちができることとは?
書店の未来を守るためには、私たち一人ひとりの意識が問われますね。
書籍を手に取ること、書店を訪れること、そして本を通じて他者とつながること。
それらの行動が、書店を支える力となるはずです。
街に書店があるということは、文化がそこに息づいている証です。その灯を絶やさないために、私たちは何をすべきなのか。
いま一度、考えないといけません。
といっても、おそらく変わらないでしょう。
だから私個人ができることは、書店で本を買うことですけど…。
まとめ
最近、「書店の危機」が新聞などで盛んに紹介されています。同時に本の紹介記事も多いですね。
私個人は、そういう記事を熱心に読みますが、筆者の子どもは(若いサラリーマンとOLです)、本をほとんど読みません。
アニメとYouTubeばかりです。YouTubeでは、本の紹介もやっていますし、読む手間が省けて重宝しますけどね。
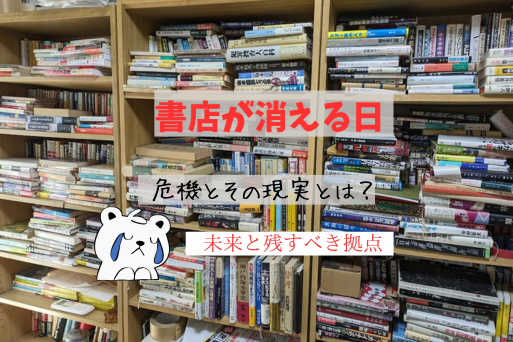


コメント